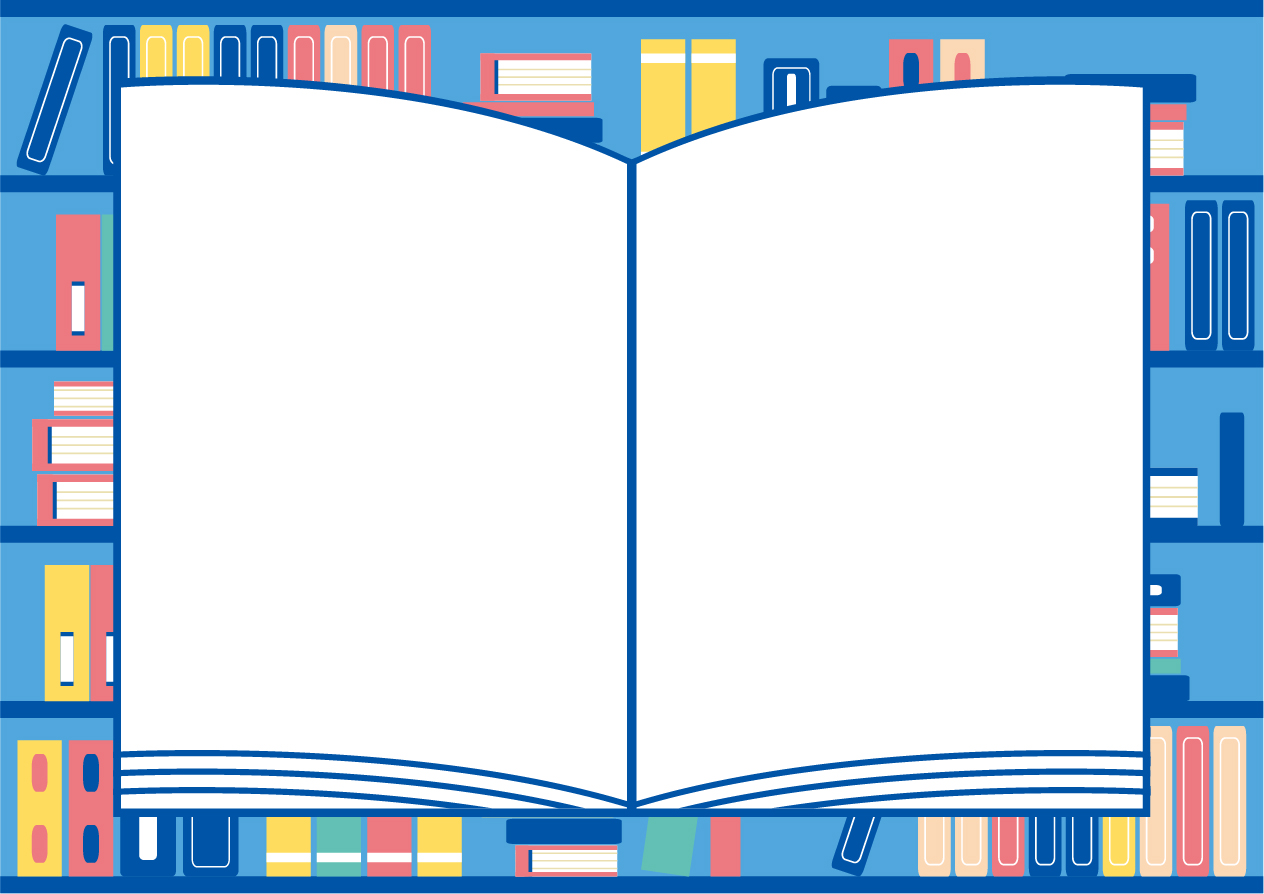
こんにちは!アルファゼミナールです。
今回は、日本語の本と英語の本で違う「開き方」に注目しながら、言葉と文化のつながりを考えてみましょう。
■日本語の本は「右開き」、英語の本は「左開き」?
日本の本を読むとき、表紙は右側にありますよね。
いっぽう、英語の本は表紙が左側。つまり、日本語の本は右から左へページをめくるのに対し、英語の本は左から右へ。
「これって、ただの習慣? それとも意味があるの?」
——実は、これには言語と文化の歴史的な背景が深く関係しているんです。
■文の“流れ”が、ページの“開き方”を決める
まず注目すべきなのは、文章を書く方向です。
| 言語 | 書き方向 | 本の開き方 |
|---|---|---|
| 日本語(縦書き) | 上から下、右から左 | 右開き |
| 英語(横書き) | 左から右 | 左開き |
日本語はもともと縦書き文化で、右から左に書いていくのが基本でした。
だから本も、右から左へとページをめくる形に。
一方、英語は古くから横書きの言語で、左から右に読むのが自然。
だから本も、左から右へめくるスタイルになったのです。
■なぜ日本語は縦書きなの?
日本語の縦書き文化は、中国の漢文の影響を受けたといわれています。
筆や毛筆を使って、巻物や書状に書く際、立って紙に向かうと、縦の方が書きやすいという実用的な理由もありました。
現代では横書きも一般的になってきましたが、
新聞・小説・和風の印刷物などでは今でも縦書き=右開きが主流です。
■デジタル時代は“どっちもアリ”!?
最近では、スマートフォンやタブレットで本やマンガを読むことが増え、ページの「めくり方」は自由に設定できるようになりました。
一部の日本のマンガも海外版では「左開き」に変えられることがあります。
このように、文化や言語の違いが、表現のスタイルにまで影響を与えるというのは、まさに言葉の面白さですね。
■学びの視点:「違い」に気づく力を育てよう
このような文化の違いは、「国語」や「英語」の学習だけでなく、
「どうしてこうなっているのか?」と考える探究心や
「他と比べてみる視点」=比較思考を養うきっかけにもなります。
たとえば:
-
なぜ日本語は“縦に読む”ことが多いのか?
-
なぜ英語は“横に読む”のか?
-
他の言語(アラビア語・ヘブライ語など)はどうなのか?
こんな問いを通じて、言語と文化をつなげて学ぶ習慣が育っていきます。
■おわりに:ことばは文化のかたち
「本の開き方」という小さな違いからも、言語・歴史・文化の深いつながりが見えてきます。
アルファゼミナールでは、こうした日常の“気づき”を学びにつなげて、
「知るっておもしろい!」と感じられる授業を大切にしています。では!
この記事を書いた人
アルファゼミナール K.T