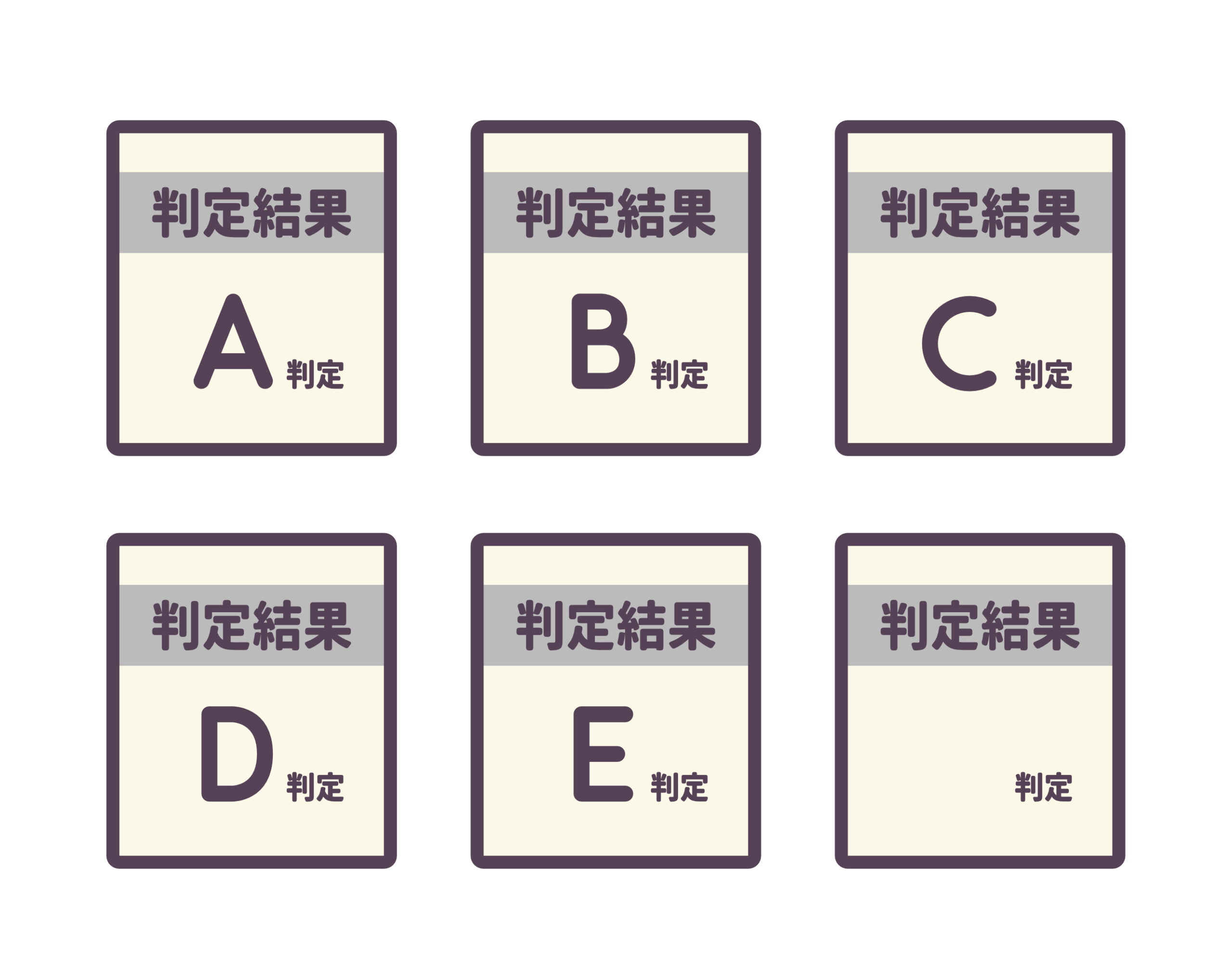
こんにちは!アルファゼミナールです。
受験生にとって大きなイベントの一つが「模試」。
結果表には A~E判定 が書かれていて、「合格可能性◯%」と出てきますが、
「この判定はどのくらい当たるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、模試判定の意味と信頼度、さらに新潟県の入試で実際に起こる「逆転合格」の例、模試をどう活かせばいいかを解説します。
① A~E判定の意味とは?
模試の判定は、過去の受験生データと照らし合わせて算出されています。一般的には以下のように解釈されます。
-
A判定(80%以上) → かなり安全圏
-
B判定(60~79%) → 合格可能性が高い
-
C判定(40~59%) → 五分五分、努力次第で変わる
-
D判定(20~39%) → 今のままでは厳しいが、逆転可能性あり
-
E判定(20%未満) → 現状は難しいが、挑戦する余地はある
👉 大切なのは「数字をそのまま信じすぎないこと」。
模試はあくまで「その時点の力を測った目安」です。
② 判定の信頼度と注意点
模試の判定は参考にはなりますが、実際の入試結果と完全には一致しません。
-
本番は 1回きりの勝負 → 模試の平均点や問題傾向とは違う
-
本番は 受験生全員が真剣勝負 → 模試よりも集中度が高い
-
模試は 志望校ごとの出願状況 を反映していない
特に新潟県の高校入試では「倍率」が毎年変動するため、模試判定がB判定でも落ちることもあれば、D判定から逆転合格することも珍しくありません。
③ 新潟県の入試で実際にあった「逆転合格」
アルファゼミナールに通う生徒でも、次のようなケースがありました。
-
中3の秋、新潟高校志望でD判定(合格可能性30%以下)
→ 苦手な数学と理科を徹底的に鍛え直し、冬休みに過去問を解き込み、
→ 本番で実力を発揮し 逆転合格! -
新発田高校志望で C判定前後を繰り返していた生徒
→ 模試直しを丁寧に行い、ケアレスミスを徹底修正
→ 本番で安定して得点し、合格を勝ち取った
👉 判定はあくまで「目安」。
最後まで努力した人にこそ、チャンスは残されています。
④ 模試後の勉強法=「復習が本番」
模試の一番大切な活用法は「復習」です。
-
間違えた問題を必ず解き直す
→ ケアレスミスか、本当に理解できていなかったかを見極める -
弱点分野をリスト化する
→ 「英語長文」「理科の電流」など、自分の穴を把握 -
次回の模試までに“弱点潰し”を計画する
→ 模試は“成績通知”ではなく“次の課題表”と考える
模試の判定を気にするよりも、模試で見えた課題をどう克服するかが一番の合格への近道です。
✅まとめ
-
模試判定(A~E)は「合格可能性の目安」であり、絶対ではない
-
新潟県入試では倍率や本番の集中度で逆転合格も多い
-
模試は“成績表”ではなく“課題リスト”として活用するのが大切
-
大事なのは「模試を受けて終わり」ではなく「復習で伸ばす」こと
アルファゼミナールでは、生徒の模試結果を一緒に分析し、**「次回までに何を伸ばすか」**を明確にした学習計画を立てています。
「判定が悪くて不安…」という人も、最後まで一緒に伸ばしていきましょう!
この記事を書いた人
アルファゼミナール K.T